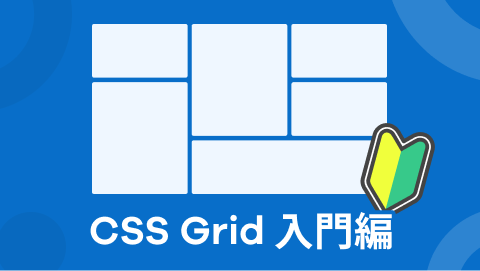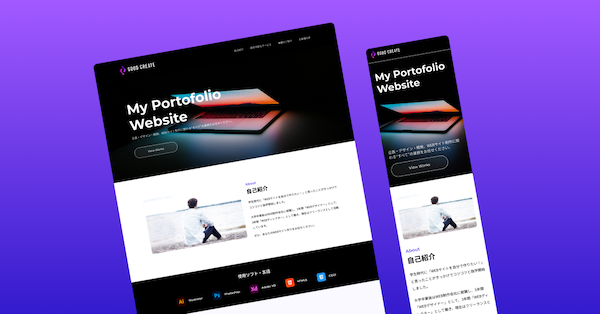更新日
#10 レイアウトを制御する|divとspanについて理解しよう
まだCSSの超初級編の講座の途中ですが、今回説明するのはHTMLのタグである<div>と<span>についての学習です。
この<div>というタグ、実はHTMLのタグの中で最も記述する回数が多いです。
では、なぜHTMLの超初級編の講座で解説しなかったのかというと、<div>と<span>というタグはCSSありきで使用するものであり、「CSS」「親要素」「子要素」を理解していないと効率的な学習ができないからです。
まずは
<span>、次に<div>という流れで1つずつ丁寧に解説していきます!